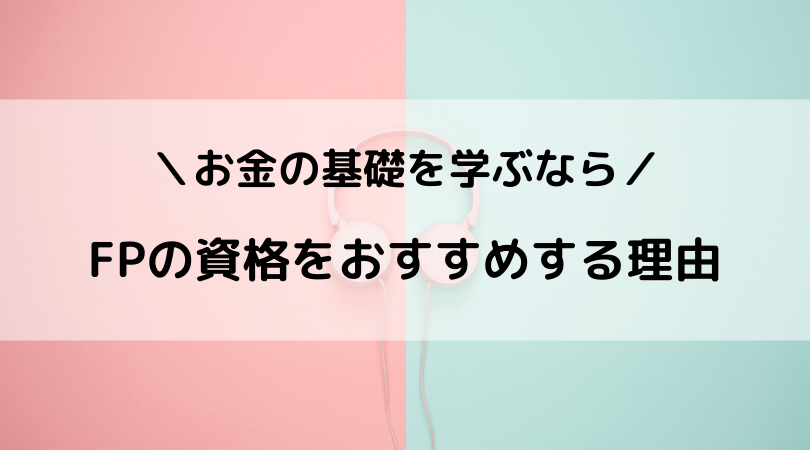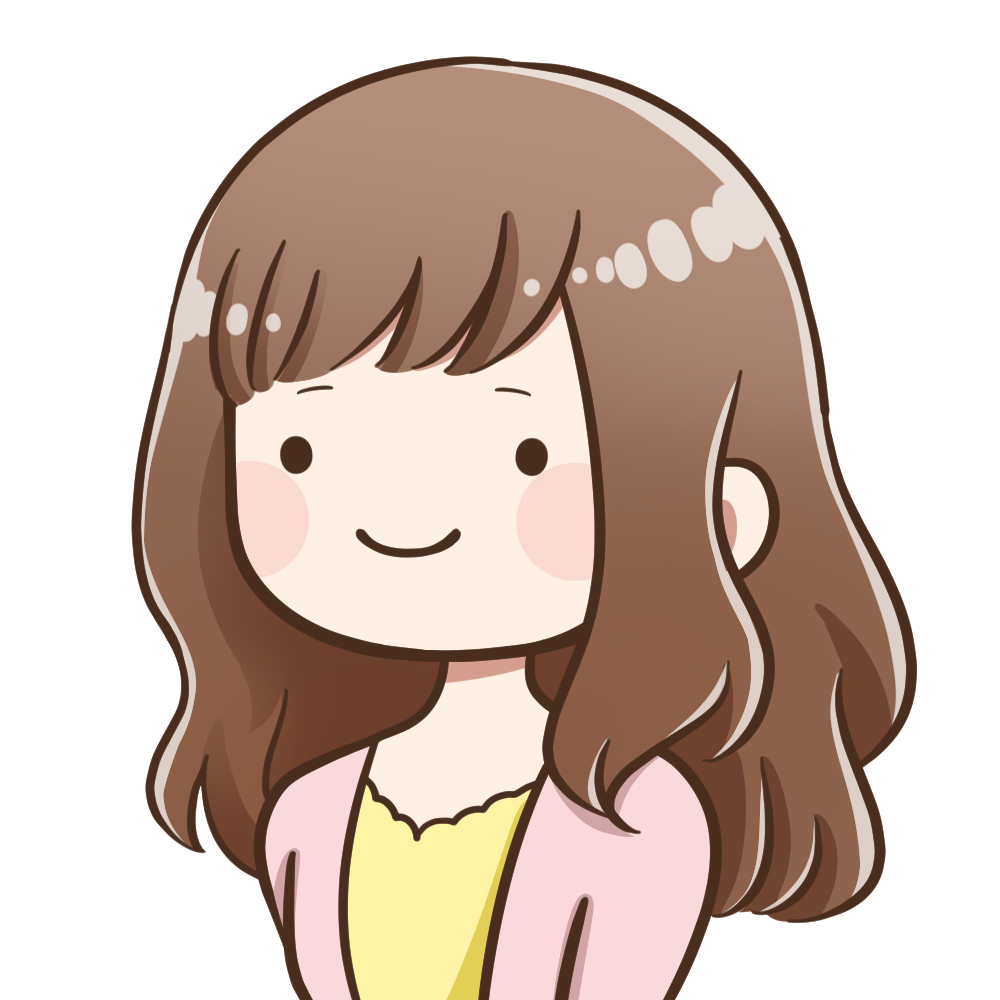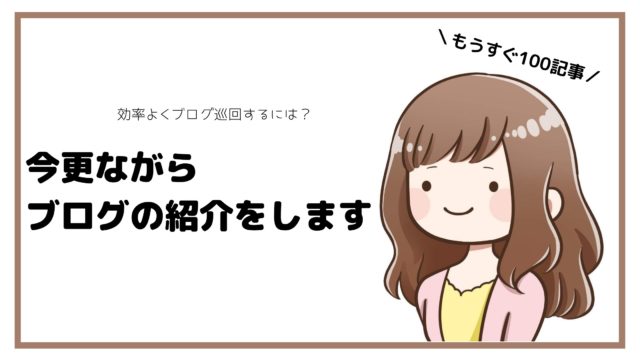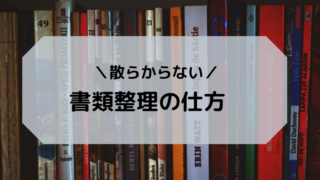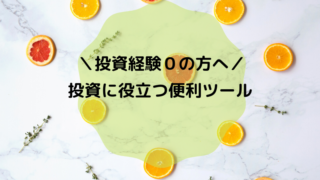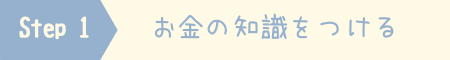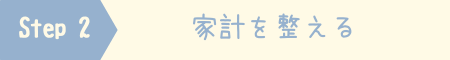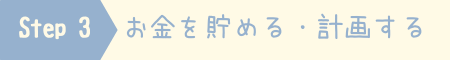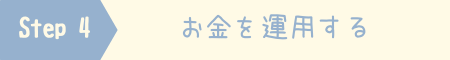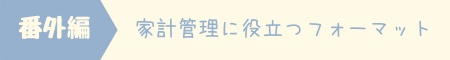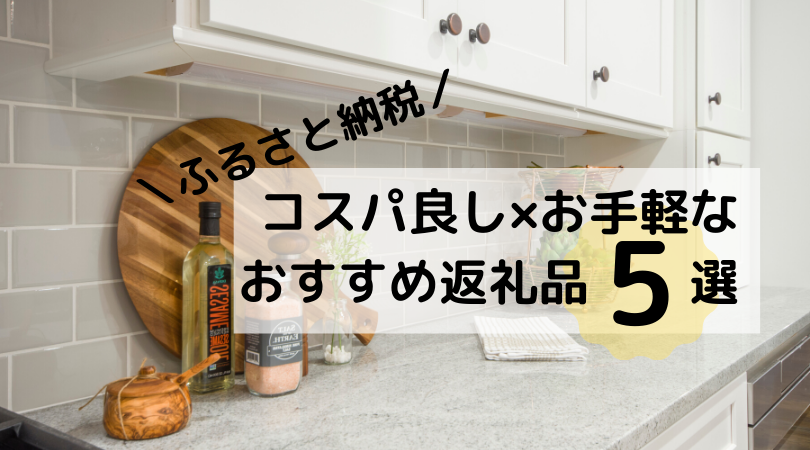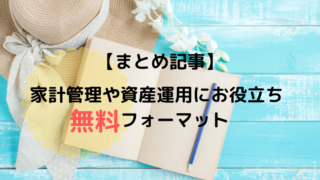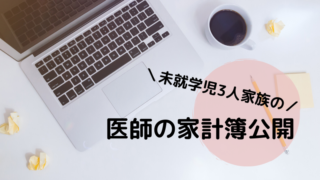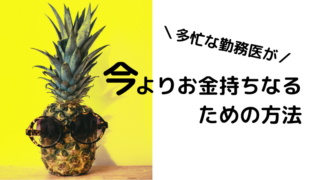この記事は医師家庭こそFP資格の必要性を説明していきたいと思います。
最近、巷でよく聞くファイナンシャルプランナー(以下、FP)。
簡単に説明すると幅広いお金の知識を持ち資産設計のアドバイザーの資格です。
私も結婚後、夫の転勤で専業主婦をしていた時に取った資格です。
名前からして難しそうなイメージですが、このFP資格は本当に取って良かった資格です!!
今回はなぜFPの知識が役に立つのか、医師家庭目線でお伝えしていこうと思います。
目次
そもそもFPで何を学べるの?

お金にまつわる知識を6つの分野に分けて学べます
1. ライフプランニングと資金計画→年金制度
2. 金融資産運用→株式、債券、貯金など投資全般
3. タックスプランニング→税金のこと
4. リスク管理→保険のこと
5. 不動産→住宅ローンなど
6. 相続・事業承継→相続税など
幅広いお金の知識を学べます。
義務教育じゃ教えくれないけど将来絶対役立ちます
お金に関することって義務教育では教えてもらっていません。
ほとんどの人がそのまま大人になり、よくわからないまま今に至っていると思います。
国民性なのか「お金の事を話すは…」とあまり周囲でもお金の話にはなりません。
しかし、結婚して家庭を持つと
「マイホームを買うには住宅ローンは?」
「教育費や老後資金はいくらかかるの?」
「貯蓄や投資はどのようにすればいいの?」
「保険って何に入ればいいかわからない」
とお金にまつわる疑問がたくさん出てきます。
そういった時に、FP資格は日々の生活から将来まで、生涯にわたって考えたいお金の疑問を解決することができ自分で正しい判断ができる手段のひとつになります。
医師家庭だとFPの知識がこんな所で役に立ちました
転勤の多い勤務医。手続きの苦痛が解消!
ローテーションで転勤が多い勤務医。その度に書類を書くことになると思います。
転勤先の病院によって年金制度が違っていたり、住民税の徴収方法が違ったり。
よくわからない~とモヤモヤしながら書いていました。
しかし、FPの勉強をしてからは社会保険制度の仕組みがわかるようになったので、書類の手続きの苦痛が解消されました。
ふるさと納税を上限ギリギリまで寄付できた
外勤先が複数ある勤務医は自分で確定申告をするので、ふるさと納税の明確な上限額がわかりません。
しかし、FPの勉強をしてから給料明細の見方がわかるようになったのでふるさと納税を無駄なく活用できるようになりました。
確定申告が苦痛じゃなくなる
税金(所得税)の仕組みって複雑ですよね。
FP資格では「所得税の流れ」を学習できるので確定申告の役に立ちました。
関連記事:なぜ節税になるの?医師が最低限知っておきたい税金の仕組み
効率の良い家計管理やライフプランが立てられた
世間一般では高収入の医師。
しかし、悩みもたくさんありませんか?
✓転勤が多く、退職金を充てにできない
✓転勤についていくため配偶者が働きにくい
✓外勤先の具合で年収の増減がある
✓税金がべらぼうに高い…
などなど。
FPの資格を勉強してから自分でライフプラン表を作ったり、老後資金のため投資を始めたり、節税のために控除を活用したりと、自分にあった家計管理やライフプランを立てられる良いキッカケになりました。
FP資格の勉強方法はコレ
ECCビジネススクールでFP2級を取りました
私は通信講座を使ってFP2級を取得しました。
普通FP資格は3級→2級と取りますがECCビジネススクールは3級を飛ばして2級から受ける講座です。
ECCビジネススクールのメリット
この講座の良かったところは何と言ってもDVD学習!!
どの分野も似たような漢字の用語や計算式が出てきて正直すごーくややこしいです。
その点、参考書に比べて耳からインプットする事で定着具合が全然違いました。
講座をスマホで見る事もでき、隙間時間に簡単に勉強できたのも良かったです。
また、過去問題と確認テストもついているので試験対策もバッチリでした。
ECCビジネススクールのデメリット
何と言ってもその価格。
59,800円なので決して安い金額ではないです。
独学に比べて費用はかかりますが、私のFP資格を取る目的は「資格を取る」でなく「知識を確実に得たい」だったので参考書より、より効果的でした。
ちなみに試験結果は95%の正答率でした★
オススメ書籍
別に資格を取らなくても良いので知識だけ得たい方はこちらの本がオススメです。
お金の教科書のように一家に一冊あってもいいかもしれません。
まとめ
FP資格の勉強をする事で以下のことを学べます。
✓お金の全般的な知識を学べる
✓社会の仕組みが分かり会社の手続きが楽に
✓ふるさと納税を有効活用できる
✓税金の仕組みがわかり確定申告に活かせる
✓ライフプランの設計の役に立つ
NEXT>【口コミ】ECCでFP資格を取ってみて良かった4つの理由